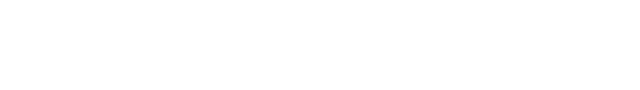肺がん
症状
肺がんは、肺にできる悪性腫瘍(あくせいしゅよう)のことです。日本ではがんによる死亡原因の1位であり、毎年多くの人がこの病気と向き合っています。喫煙(たばこ)との関連が深く、特に50代以上の男性に多く見られる病気ですが、女性や非喫煙者にも発症するケースが増えています。
肺がんの厄介なところは、初期にはほとんど自覚症状がないという点です。そのため、健康診断やがん検診で偶然見つかることも多く、発見が遅れると進行してしまうことがあります。
肺がんの主な症状は次の通りです:
- 咳(せき)が長引く(2週間以上)
- 痰(たん)に血が混じる(血痰)
- 声がかれる
- 息切れ、胸の痛み
- 体重が減る、食欲が落ちる
- 発熱が続く、体がだるい
症状はがんの場所や大きさ、転移の有無によって変わります。たとえば、がんが気管支に近いところにできれば咳や血痰が出やすく、肺の外側にできると胸の痛みが出ることがあります。
また、肺がんはリンパ節や骨、脳、副腎などに転移しやすい性質があります。そのため、がんが肺以外の場所に広がったことで症状が出ることもあります。
検査、診断
肺がんを見つけるためには、画像検査・血液検査・細胞検査などを組み合わせて行います。初期のがんは症状が少ないため、健康診断やCT検査が早期発見のカギになります。
1. 胸部レントゲン検査
肺の影や異常があるかどうかを調べます。ただし、小さながんや肺の外側にあるものは写りにくいため、初期のがんは見逃されることもあります。
2. 胸部CT検査(コンピューター断層撮影)
レントゲンよりも詳しく肺の内部を立体的に調べることができます。がんの大きさや形、リンパ節への転移の有無などを確認します。低線量CTを使った肺がん検診も広まりつつあります。
3. 喀痰細胞診(かくたんさいぼうしん)
痰の中にがん細胞が混ざっていないかを調べる検査です。気管支の近くにできるがん(中心型肺がん)では、比較的見つかりやすいです。
4. 気管支鏡検査(きかんしきょう)
内視鏡を使って、肺の中を直接観察し、組織を採取(生検)する検査です。がんがあるかどうか、またどんなタイプのがんかを詳しく調べることができます。
5. 血液検査(腫瘍マーカーなど)
肺がんの種類によっては、CEA、CYFRA、ProGRPなどの腫瘍マーカーが上昇することがあります。ただし、これだけで診断することはできません。
6. PET検査・MRI・骨シンチグラフィーなど
がんが肺の外に転移していないかを調べるために、全身の詳しい検査を行うことがあります。
肺がんにはいくつかの種類があり、大きく分けて以下のように分類されます:
- 非小細胞肺がん(腺がん・扁平上皮がんなど):全体の約85%
- 小細胞肺がん:進行が速いが、薬が効きやすい特徴があります
がんの種類と進行度(ステージ)によって治療方針が変わるため、正確な診断が治療の第一歩です。
治療
肺がんの治療は、がんの種類(非小細胞か小細胞か)、ステージ(進行度)、患者さんの体力や希望によって異なります。複数の治療法を組み合わせて行うこともあります。
手術(外科治療)
がんが肺の中だけにとどまっていて、全身状態がよい場合には、手術でがんを切除します。肺の一部(区域切除・葉切除)や、時に肺全体を取ることもあります。
術後は肺活量が減るため、呼吸機能を評価してから手術の可否を判断します。
放射線治療
手術ができない場合や、がんが限局している場合には、放射線でがんを狙い撃ちする治療を行います。定位放射線治療(ピンポイント照射)は、体への負担が少なく、早期がんにも適応されます。
薬物療法(化学療法・分子標的薬・免疫療法)
進行がんや転移がある場合は、体全体に働く治療(全身療法)が中心になります。
- 化学療法(抗がん剤):がん細胞の増殖を抑える
- 分子標的治療薬:EGFRやALKなど、特定の遺伝子異常があるがんに対して使われる薬。副作用が少なく効果が高いケースも
- 免疫チェックポイント阻害薬(オプジーボ、キイトルーダなど):免疫の力でがんを攻撃する、新しい治療法
近年はがんの遺伝子を詳しく調べて、その人に合った薬を選ぶ「個別化医療」が進んでいます。
緩和ケア
治療が難しい状態でも、痛みや呼吸困難、精神的なつらさを和らげるサポートが受けられます。患者さんとご家族のQOL(生活の質)を守る大切な医療です。
予防と早期発見のために
- 禁煙は最大の予防策です
- 年に一度の肺がん検診(レントゲン)は早期発見のカギ
- 最近では、低線量CTによる肺がん検診が注目されています(高リスク者に有効)
ご相談ください
肺がんは進行が早いこともある一方で、早期に見つかれば治療で治る可能性もあります。「長引く咳」「血痰」「声のかすれ」などがある場合は、早めの受診をおすすめします。