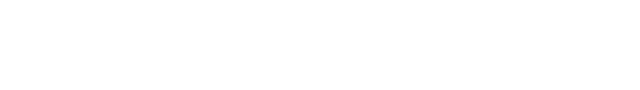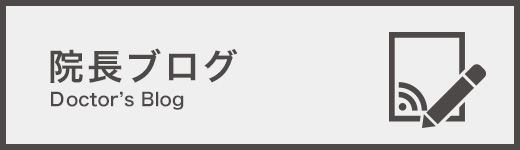息苦しさ・息切れ
息苦しさ・息切れとは?
「息苦しさ」や「息切れ」は、呼吸がうまくできない、息が足りないと感じる状態です。運動したあとにハァハァ息が上がるのも息切れの一種ですが、特別な動きをしていないのに息苦しさを感じるときは、体のどこかに問題があるかもしれません。
息苦しさ(呼吸困難)
普段どおりに呼吸しているのに、空気がうまく吸えない・吐けないように感じる状態です。胸がつかえる感じ、のどが詰まったような感じ、呼吸が浅くなるといった症状を伴います。
息切れ
歩いたり、階段を上ったりといった少しの動作で呼吸が苦しくなり、すぐに立ち止まってしまうような状態です。「体力がないだけ」と思われがちですが、病気のサインであることもあります。
息苦しさや息切れにはいくつかの原因があります。
- 肺の病気:ぜんそく、肺炎、肺気腫、間質性肺炎、気胸など
- 心臓の病気:心不全、狭心症、心筋梗塞など
- 血液の病気:貧血など(酸素を運ぶ力が弱くなる)
- 精神的な要因:ストレスや不安、過換気症候群など
- 体の動かしすぎ:健康な人でも運動のあとには息が上がります
症状の出方にもいろいろあります。たとえば、
- 朝は平気なのに、夜になると苦しくなる
- 階段でだけ苦しくなる
- 寝ると苦しいが、座ると楽になる
など、細かい違いが診断のヒントになります。
息が苦しいという感覚は人によって差がありますが、放っておいてよくなるとは限りません。とくに突然苦しくなったとき、安静にしていてもつらいときは、早めに医療機関を受診しましょう。
息苦しさ・息切れの検査
息苦しさや息切れの原因を調べるには、まずは「どんなふうに苦しいか」をしっかり聞き取ることが第一歩です。そのうえで、必要に応じて次のような検査を行います。
【1】問診・診察
いつから息が苦しいか、運動すると悪化するか、横になるとつらいか、せきや痰、胸の痛みはあるかなどを詳しく聞きます。のどの音や呼吸の音を聴診器で確認します。
【2】胸部レントゲン検査
肺や心臓の形、大きさ、異常がないかを確認します。肺炎、気胸、心不全、間質性肺炎などの発見に役立ちます。
【3】血液検査
血中の酸素を運ぶ「ヘモグロビン」の量や、体内の酸素・二酸化炭素のバランス、心臓に負担がかかっていないか(BNP値)などを調べます。感染症や貧血の有無もわかります。
【4】心電図検査
心臓の動きに異常がないか調べるための検査です。狭心症や心筋梗塞、不整脈などを見つけることができます。
【5】呼吸機能検査(スパイロメトリー)
空気を吸ったり吐いたりする力を調べる検査です。ぜんそくやCOPD(慢性閉塞性肺疾患)、間質性肺炎など、肺の病気があると呼吸の数値が低下します。
【6】動脈血ガス検査
血液中の酸素や二酸化炭素の量を直接調べる検査です。重い呼吸障害があるときに行います。
【7】心エコー(超音波)検査
心臓の形や動きを見る検査で、心不全や弁膜症などの異常を見つけることができます。
【8】酸素飽和度(パルスオキシメーター)
指先に機械をつけて、血液中の酸素の量を測る簡単な検査です。数値が低いと、酸素不足の可能性があります。
検査は体への負担が少ないものから始め、必要があれば段階的に行います。原因を正しく見つけて、適切な治療につなげることが大切です。
息苦しさ・息切れの治療
息苦しさや息切れの治療は、原因となる病気によって異なります。ここでは代表的な治療を紹介します。
【1】肺の病気が原因の場合
ぜんそくやCOPD(慢性閉塞性肺疾患):
吸入薬(気管支を広げる薬、炎症を抑える薬)を使います。吸入薬は気道に直接届くため、効果的で副作用も少ないです。
- 肺炎: 原因が細菌であれば抗生物質を使います。重症の場合は入院や点滴が必要になることもあります。
- 間質性肺炎: ステロイドや免疫を抑える薬を使って、肺の炎症や進行を抑えます。定期的な検査や呼吸リハビリも大切です。
- 気胸: 肺に穴があいて空気が漏れる病気で、胸に管を入れて空気を抜く処置が必要になることもあります。
運動や姿勢のくずれ、疲労によるものが多く、痛み止めの薬や湿布などで対応します。安静にしていると改善することがほとんどです。
【2】心臓の病気が原因の場合
- 心不全: 心臓の働きが弱くなっている状態で、利尿剤や血圧を下げる薬を使います。塩分の制限や体重管理も必要です。
- 狭心症・心筋梗塞: ニトログリセリンなどの薬を使ったり、心臓の血管を広げる治療(カテーテル治療)を行います。命にかかわる病気なので、早期発見が重要です。
【3】貧血が原因の場合
鉄分やビタミンなどを補うことで、酸素を運ぶ力を回復させます。重い場合は輸血が必要になることもあります。
【4】ストレスや過換気症候群が原因の場合
呼吸が浅く速くなりすぎて酸素と二酸化炭素のバランスがくずれる状態です。落ち着いた呼吸や、心理的なサポートが効果的です。必要に応じて抗不安薬を使うこともあります。
【5】生活の中でできる工夫
- 無理な運動は避ける
- 部屋を換気して空気をきれいに保つ
- 禁煙する
- 栄養と水分をしっかりとる
- 医師の指示通りに薬を使う
ご相談ください
息苦しさや息切れは、体のSOSサインかもしれません。苦しさを我慢せず、「いつ・どんなふうに苦しくなるのか」を記録しておくと診察の役に立ちます。気になる症状があるときは、どうぞお気軽にご相談ください。
当院では各種クレジットカード、およびPayPayでの決済が可能です。
クレジットカード:VISA、Mastercard、JCB、Diners Club、American Express、JACCS、Discover
QRコード:PayPay